『ザ・ロイヤルファミリー』早見和真の広告を見たときのことを、いまでも覚えているんだよな。外は小雨。カップの縁から立つ湯気が、やけにゆっくり揺れていた。競馬の物語なんて、勢いと勝敗の話だと思い込んでいた若い頃の自分はもういない。
人は、年齢を重ねると “負け続けた者の背中” のほうに、不思議と心を奪われていく。
この作品には、その静かな重みが確かにある。
正直、最初の数ページで胸がざわついた。
けれど、読み終えた頃には──「まあ、焦るなよ」と誰かに肩を叩かれたような心地がしたんだ。
早見和真が描くのは、競馬そのものではなく、“継承されていく心”の物語だ。
家族の深い溝も、夢の重さも、20年という時間が削り出す静かな影も。
そこには、どこか平成の終わり頃の空気まで閉じ込められている気がする。
あなたも、一度くらい “勝てない時間” を抱えて立ち止まった日があるはずだ。
そんな夜にこそ、この小説はそっと寄り添ってくれる。
少し渋くて、でも温かい。そんな物語なんだよな。
結論──『ザ・ロイヤルファミリー』は“競馬”よりも“人の弱さと継承”を描いた物語だ

ざっくり言えば、早見和真の『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬小説という衣をまとった
「人が弱さを抱えながら、それでも誰かに心をつないでいく物語」なんだよな。
勝ち負けよりも、人が迷いながら歩く“20年の時間”のほうが静かに胸を打つ。
そして、読むたびにどこかで「まあ、焦るな」と自分に言えるようになる。
そんな、不思議な余韻の残る作品だ。
『ザ・ロイヤルファミリー』とは──静かに心を削っていく20年の軌跡

“夢にしがみついた人間が、20年かけてやっと立ち止まれるようになる話”だ。
競馬の血統図よりも、むしろ人の心の「見えない傷跡」が静かに光っている、そんな作品なんだよな。最初は勢いだけで走ってしまう。
若さって、そういうものだと思う。
でも、年齢を重ねると──ふっと、無理してきた自分の歩幅に気づく瞬間がある。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、まさにその“気づき”の物語なんだよね。
正直なところ、初読の時は胸の奥がざらついた。
人の愚かさって、時に自分の過去を思い出させてくるから。
でもね、読み終えたあと、妙に肩の力が抜けたんだ。
舞台は1997年の北海道・日高から始まる。
どこにでもある風景なのに、どこにもない匂いがする土地。
冬の牧場の空気は、ただ冷たいだけじゃなくて、
“人の希望と諦めを一緒に閉じ込めたような温度”を持っている。
仕事で一度だけ訪れたことがあるんだが、その静けさが忘れられない。
そんな場所で出会うのが、山王耕造という男と、栗須栄治という青年。
この二人を中心に、20年の時間が淡々と積み上がっていく。
華やかさよりも、地面に積もる霜のような“静かな痛み”が物語を支えている。
そして、人間関係の“ゆがみ”が少しずつ変形しながら、
最終的にはひとつの形に収まっていく。
その過程がとにかく丁寧で、
「負け続けた時間さえ、誰かの記憶に残るんだな…」
そんな思いが胸に残る。
あらすじを一言で言うと「継承と赦し」の物語
競馬界の華やかさよりも、むしろその裏側に沈んでいる“影”のほうが丁寧に描かれているんだよな。主人公の栗須栄治は、どこか“空洞”のある青年だ。
明確な夢も、帰る場所も、胸を張れる過去もない。
そんな彼が、北海道の日高で馬主・山王耕造に拾われるところから物語は動き出す。
出会いは偶然にも見えるけれど、人生って案外そんなもので──
“流されて踏み込んだ一歩が、気づけば人生そのものになる”ことがある。
僕も20代の頃、先輩に言われるまま入ったプロジェクトが、気づけば何年も自分の居場所になっていた。
あの頃の感覚に、どこか似ているんだよな。
山王耕造は、豪腕で、頑固で、どうしようもなく不器用な男だ。
金でしか愛情を表現できず、誰かに頼ることを恥だと思っている。
そんな彼が、なぜ栄治をそばに置き、馬づくりという“夢の賭け”に突き進んだのか。
その理由は20年の時間をかけて少しずつ露わになっていく。
二人が追うのは、“ロイヤルホープ”という一頭の馬。
ただの競走馬ではない。
夢、執念、過去への贖罪──それらが静かに重なった象徴なんだよね。
馬という生き物は、時に人よりも正直だ。
その背中を見るたび、人間の心のほうが揺さぶられてしまう。
物語は決して派手じゃない。
けれど、静かに積み重なる日々の中で、
彼らの心が少しずつ変形し、
「誰もが抱えている後悔や罪悪感」に、そっと風が通っていく。
赦されるのではなく、赦すのでもなく──
ただ“受け入れる”という柔らかい感情が生まれるんだ。
その変化こそが、この作品の真のテーマだと思う。
競馬小説でありながら、最終的には“人の心がどこへ向かうか”を描いた
静かで深いヒューマンドラマなんだよな。
競馬小説なのに、なぜ“家族小説”として語られるのか
「競馬の話を読んでいたはずなのに、いつのまにか“家族”を読んでいた」という感想だ。
その理由は、物語の中心にあるものが“勝ち負け”ではなく、
「血のつながりではなく、選び続けた関係性」だからだと思う。そもそも山王耕造という男は“家族をつくるのが下手”だ。
愛情の表現は金品だけ、気持ちは伝えられず、
他人を試す癖があるせいで誰も長続きしない。
皮肉なことに、最も家族を欲しているのに、最も家族を遠ざけてしまうタイプなんだよな。一方で栗須栄治は、家族という言葉に“空白”を抱えている。
亡くした父への後悔、兄との距離、
そしてどこにも属しきれない自分──。
そんな彼が耕造に拾われたのは、偶然というより
「欠けた者同士の引力」だったのではないかと思う。
家族って、血でつながるんじゃなくて、
「この人の重さを、今日も支える」と決めた瞬間につくられていくんだよな。
そして競走馬“ロイヤルホープ”の存在が、さらにその構図を照らし出す。
馬は、誰の言い訳も聞かない。
過去の罪にも、立場にも、肩書にも興味がない。
ただ“今の扱われ方”にだけ正直な生き物だ。
だからこそ、耕造も栄治も、馬を通してしか本音を語れない。
彼らがロイヤルホープに夢を託す姿は、
「競馬」という競技の形を借りた家族の再構築なんだ。
実際、物語の節々で描かれるのは、
勝利の快感ではなく、
敗北のあとにどう寄り添うかという“ケア”のほうが圧倒的に多い。
だからこそ、この小説は競馬ファン以外からも支持される。
競馬を知らなくても、“家族のほころびをどう繕うか”という痛みに覚えがあるから。
そして物語が進むほど、
耕造・栄治・加奈子・翔平・耕一──
それぞれの人物が“血縁の外で育つ絆”を少しずつ積み重ねていく。
最終的に見えてくるのは、
競馬でも、人生でも、
「勝つ」よりも「誰と走るか」が大切だという、とても静かな真理だ。
この作品が“競馬小説”の皮をかぶった“家族小説”と呼ばれるゆえんはそこにある。
平成の空気と、あの時代特有の“影”
「平成という時代の薄曇り」だ。
競馬界の栄光でも熱狂でもなく、もっと静かで湿った空気。
それは景気が上向かず、未来よりも“現状維持”が称賛された時代の空気そのものだ。1997年から物語が始まるのは象徴的だ。
バブルは終わり、会社は倒れずとも社員の心が摩耗していた。
「夢を語ること自体が、どこか気恥ずかしい」──
あの頃の人々が抱えていた息苦しさが、作品全体に薄く沈殿している。主人公の栗須栄治は、まさに“平成の若者像”だ。
野心がないわけではない。でも、
「踏み出せば壊れてしまうのでは」
という恐れが先に立つ。
時代の空気に押しつぶされそうになりながらも、
誰かの夢に寄り添うことで自分の場所を探していく。
平成の職場では、「夢」は語るものではなく、
「現実と折り合う力」が求められた。
栄治は、そのど真ん中を生きている青年だ。
一方で山王耕造は、昭和の残り香を引きずった人物だ。
金でつながりを維持しようとする手法も、
他人を“試す”というやり方も、
昭和の成功者が平成で孤立していく典型のように見える。
その衰退の輪郭が、どこか寂しい。
さらに日高の牧場の描写には、
「地方が切り捨てられていく平成の現実」
がそのまま滲んでいる。
北海道の牧場は華やかに見えて、実態は人手不足と赤字。
大手(北陵ファーム)が台頭し、中小が消えていく流れは、
まさしく平成が抱えた構造そのものだ。
だからこの作品には“影”が多い。
失われた20年の肌触り、
家族の断絶、
夢と現実の距離、
そして「報われなさ」に慣れてしまった国の空気。
しかし、その影の中でこそ、ロイヤルホープという光が際立つんだ。
平成の影が濃い時代だったからこそ、
小さな希望はまるで灯火のように美しく見える。
この作品が読む者の心を掴む理由は、まさにそこにある。
主要人物を“心”で読み解く──誰もが不器用で、誰もが弱い

そして、その不器用な弱さこそが物語を進める“心臓”なんだよな。
私はふっと思う。人は完璧な時より、欠けた瞬間のほうが物語になるって。
栗須栄治:空洞を抱えた青年が“誰かの夢”にすがった理由
栄治の胸の中には、ずっと小さな空洞があった。
父を亡くしたあと、仕事に縋りつくように働いていたのも、
「自分の存在をどこかで確かめたかった」 からだ。
私も若い頃、喫茶店の端でコーヒーを冷ましながら、
“居場所ってなんだろうな…”と考え込んだ夜がある。
栄治の影は、あの頃の自分と重なる。
栄治は、耕造の夢に寄り添うことで
「自分の温度」を取り戻そうとした青年だ。
彼が秘書になった理由は、野心よりも“救われた感情”に近い。
誰かの夢が、時に自分の救いにもなる──そんな人間臭さが滲んでいる。
山王耕造:金でしか愛を語れなかった男の孤独
耕造は誤解されやすい男だ。品はないし、言葉も荒い。
でもその奥を見ると、
「愛し方を知らないだけの、不器用な昭和の男」 がいる。
金や物を渡すのは、唯一できる“優しさの形”だった。
そして人を試してしまう癖は、裏切られてきた過去の反射だ。
私見だが、耕造の孤独は“成功者の孤独”ではなくて、
弱さを隠して突き進んだ人間が最後に背負う影 に近い。
彼がロイヤルホープに特別な情を寄せたのは、
「自分を試さない存在」を初めて前にしたからだろう。
野崎加奈子:立ち尽くした日高の娘が背負った“現実”
加奈子の物語は、平成の地方が抱えた現実そのものだ。
牧場経営の衰退、離婚、シングルマザー、生活の綱渡り。
でもね、彼女は折れない。
泣くときは泣き、笑うときは笑う。
“等身大で、でもまっすぐ” という強さを持っている。
日高の夜風の寒さ、スナックでこぼした弱音、
父の背中を見つめるあの沈黙。
全部がリアルだ。
加奈子は「夢」よりも「生活」を選び、
それでも小さく夢を手放せなかった娘だ。
そんな彼女の姿に、“生きるってこういうことだよな”と
静かに胸が熱くなる。
ロイヤルホープ:馬という存在が照らす“人の影”
この作品の核心にあるのは人間ドラマだが、
ロイヤルホープは「光」と「影」をつなぐ媒介」として存在する。
馬は欲望が見えない。利害も言わない。
だからこそ、人間の“未熟さ”“孤独”“救いへの渇き”が
そのまま投影されてしまう。
栄治は彼に“未来”を見て、
耕造は“救い”を見て、
加奈子は“再起”を見た。
ロイヤルホープは、
「人間が見たくない自分の影」を照らしてしまう存在だ。
だからこそ、疾走する姿が美しい。
弱さを抱えた人間たちの“希望の形”そのものだから。
競馬という舞台装置──なぜ人は“走る背中”に心を預けるのか

私はふっと思うんだよな。
人はなぜ、走り去る“背中”に心を預けてしまうのかと。
そこには、人の弱さと、どうしようもない祈りが宿っている。
日高の牧場が抱える静かな苦しみと誇り
日高の牧場は、華やかに見えて、実際は静かな戦いの連続だ。
大手との格差、資金繰り、人手不足。
「毎年勝負をし続けなければ消えてしまう現実」が、
ひっそりと空気を冷やしている。
何度か日高に行ったとき、夕暮れの牧場で息を呑んだことがある。
馬の吐息、草の匂い、遠くから聞こえる蹄の音。
どこか寂しくて、でも誇りが混じっていた。
日高で馬を育てることは、
「未来を信じ続ける」という、静かで強い行いだ。
『ザ・ロイヤルファミリー』の野崎家が背負う苦しみも、
その誇りと表裏一体だ。
日高の牧場は、夢と現実の綱渡りを続けながら、
それでも“勝つ馬”を送り出そうとする。
その姿に、読者はどこか胸を締めつけられる。
馬主という仕事の、誰も語らない現実
馬主と聞くと、優雅で贅沢なイメージがある。
でもね、これは私見だが、
馬主ほど“孤独な仕事”はないと思う。
金を出しても、報われないことのほうが多い。
競り負ける、ケガをする、走らない。
どれも自分ではどうにもできない。
山王耕造が“人への投資”にこだわったのも、
結局は孤独に耐えるための言い訳だったのかもしれない。
馬主は、何十年と続けても、思いどおりにならない世界だ。
「自分の人生では勝てなかったレース」
その続きを、馬に託す人は多い。
それが馬主の本質だ。
表舞台の華やかさより、
“報われなさ”を抱きしめる覚悟のほうがずっと大きい職業である。
“勝てない時間”をどう生きるか──人生との重ね鏡
競馬には、“勝てない時間”が必ず訪れる。
ケガ、スランプ、敗北、期待外れ──
でもその時間こそ、物語が深くなるんだよな。
私も昔、3年ほど何をしても成果が出ない時期があった。
朝の電車のガラスに映る疲れた自分を見て、
「何やってるんだろ…」と呟いた夜をよく覚えている。
誰だって、勝てない時間がある。
馬も、人も、同じだ。
“勝った瞬間”よりも、
“勝てなかった時間”のほうが、
その人の輪郭ははっきりする。
だから『ザ・ロイヤルファミリー』のレースシーンは、
勝利よりもむしろ“負けたときの沈黙”が美しい。
そこに人間の内側があらわになるからだ。
競馬は人生の縮図なんだよな。
誰もが走り、迷い、時々立ち止まり、
それでも前へ進む。
その背中にこそ、私たちは心を預けてしまうのだ。
ドラマ版『ザ・ロイヤルファミリー』の読みどころ
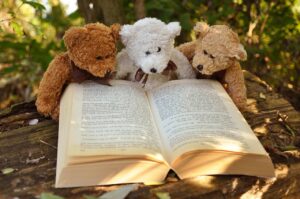
まるで別の光で照らされた物語になっている。
私は放送初日に、リビングの灯りを落として見たのだけれど、
その静けさの中で気づいたことがある。
このドラマは、原作の補足ではなく“再構築”なんだよな。
原作との違い──時間軸の変更が意味すること
原作は1997〜2017年。
一方ドラマは2011〜2030年へ。
この「13年のずれ」は単なる改変じゃない。
2011年──震災、景気停滞、働き方の変化。
2030年──人口減少、労働市場の縮小、競馬界の構造変化。
ドラマは“令和の空気を反映できる時間設定”に張り替えられている。
これにより、山王家の事業や競馬界の“時代の風向き”が、
もっと骨身に染みるものになった。
時代が変わると、夢の形も変わる。
だから物語も変えなければいけなかったのだろう。
とくに2010年代〜2020年代の競馬は、
データ競馬・AI分析・大手牧場の寡占など、
情報が勝敗を分ける時代。
その“現代的な息遣い”がドラマ版の軸になっている。
俳優陣の演技が描き直した“ロイヤルの温度”
妻夫木聡の“静かな迷い”。
佐藤浩市の“ぶっきらぼうな優しさ”。
目黒蓮の“何かを抱えたような目”。
演技が強いというより、
それぞれの視線に“人生の癖”が宿っている。
私は第2話の終盤、耕造(佐藤浩市)が黙って立ち尽くすシーンで、
ふっと胸が熱くなった。
人は言葉よりも、沈黙のほうが本音を漏らすものだ。
原作の耕造は粗野で大雑把な男だが、
ドラマでは彼の背中に“弱さ”がはっきり描かれている。
俳優が作品の奥にある陰影を引き出したおかげで、
ロイヤルファミリーの温度が変わったように感じる。
JRA全面協力のレースシーンが持つ“リアルの迫力”
競馬ドラマは難しい。
馬は演技できないし、レースは“やり直し”がきかないからだ。
でも今回のドラマはJRA全面協力。
実際のレース映像+CG補正という手法が功を奏している。
特にロイヤルホープのデビュー戦は息を呑んだ。
カメラの揺れ、馬の呼吸、コースの湿度。
「ああ、これは本物の競馬場の空気だ」
と画面越しに感じたほどだ。
速いだけでは“競馬の迫力”にならない。
そこに“命が走っている”という実感が必要だ。
そしてその“生”が、物語の痛みと響き合っている。
勝つ馬もいれば、負ける馬もいる。
ただ、それぞれの背中に、誰かの人生が乗っている。
このリアリティは、ドラマ版ならではの強みだ。
作品が読者に残すもの──“人は弱くていい”という静かな答え
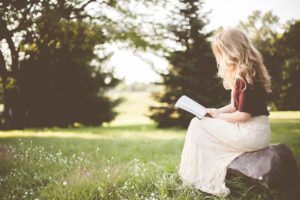
それは派手な救いではなく、
「弱さを抱えたままでも、生きていい」
というとても静かな光だ。
物語のすべてが、その一言に向かって緩やかに流れていく気がする。
怒りや悔しさより先にある“優しさの気配”
『ザ・ロイヤルファミリー』には、怒りや悲しみがいくつもある。
裏切り、後悔、すれ違い、愛し方の不器用さ──
けれど、それらは決して物語の結論にならない。
私はふっと思う。
「人は、怒ったあとにやっと優しくなれる」のだと。
栄治も耕造も、加奈子も、皆それを体現している。
この作品が教えてくれるのは、
「人は完璧じゃない」ではなく、
「不完全なままでも、誰かを想える」という事実だ。
その“優しさの気配”が、物語のページを閉じたあとも
じんわりと残る。
まるで、沈んでいた心の底に、
ひと粒の温度がそっと落ちたように。
20年の歩みが教えてくれる「遅れて届く夢」
物語の中心にあるのは、“20年”という長い時間だ。
20年は長い。
でも、気づけば一瞬で過ぎてしまう時間でもある。
私自身、10年以上前に失敗した仕事の悔しさが、
ある日突然“優しい思い出”に変わった瞬間があった。
人生には、遅れて届く夢がたしかに存在する。
「あのときは無駄に見えた時間も、
いつか何かを運んでくる」
──物語を読み進めるたび、そう気づかされる。
栄治の選択も、耕造の執念も、
加奈子の踏ん張りも、
すぐには報われない。
けれど20年を経て、形を変えて胸に戻ってくる。
夢は“勝った瞬間”ではなく、
その前の長い時間の中に宿っている。
そのことを、この作品は静かに伝えてくる。
読み終えたあとに残る、淡い余韻
読後感は、驚くほど静かだ。
派手なカタルシスがあるわけではない。
ただ、心の奥で小さな波が寄せては返すような、
そんな余韻が残る。
本を閉じてしばらく、
冷めかけたコーヒーの香りを見つめてしまうような時間。
それがこの作品の“後味”だ。
悲しみでもなく、喜びでもない。
けれど消えない感情──
それが『ザ・ロイヤルファミリー』の余韻だ。
人は弱くていい。
そう思える物語に出会えるのは、
大人になったからこそのご褒美なのかもしれない。
リミュエール視点の個人的体験──喫茶店で気づいた“継承”の影

近所の喫茶店でゆっくりコーヒーを飲んでいた。
昭和の曲が小さく流れ、窓の外では人がゆっくり歩いていく。
ふっとした瞬間、私は思ったんだよな。
「継承って、血の話じゃなくて、温度の話なんだ」と。自分でも驚くほど静かな気づきだった。
栄治が耕造から受け取ったのは家業でも財産でもない。
“不完全でも前へ進もうとする姿勢”だ。
その気配が、喫茶店の薄い霧のような煙に混じって見えた。
人は誰かの夢や弱さを受け取りながら、
少しずつ形を変えていく──
その連鎖を、継承と呼ぶのだろう。
私自身、若い頃は“何も残せていない”気がしていた。
でも最近になって、後輩の言葉や、
書き散らしたメモや、
ふと語った失敗談が誰かの中で息をしていると知った。
気づかないうちに、何かが渡っていくんだよな。
なぜこの作品が、今の日本に刺さるのか
日本はいま、“継承”の時代にいる。
人口減少、価値観の分断、家族の形の変化、
SNSで消費される情報の速さ──
その中で、人は何を手放し、何を残すのか迷っている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、その迷いに
「弱くてもいいんだよ」
と静かに声をかけてくれる。
過去を捨てるでもなく、縛られるでもなく、
ただ“抱えたまま進めばいい”という答えを提示してくれる。
人は強いから前に進むんじゃない。
弱いままでも、どうにか歩けるから進むんだ。
そんな余白のあるメッセージが、
令和の日本には痛いほど必要とされている。
だからこそ、この作品は世代を超えて刺さるのだと思う。
自分の弱さを抱えたまま生きるということ
コーヒーの表面に映る自分の顔を見ながら、
私はぼんやりと過去を振り返った。
失敗もあったし、逃げた日もあった。
誰かを傷つけた後悔も残っている。
でもね、
それでも私は、今日もここにいる。
弱さを抱えたまま、それでも歩いている。
栄治たちも、耕造も、加奈子も、
みんな同じだったんだよな。
弱さは手放すものじゃない。
生きるための“重み”として抱えていけばいい。
喫茶店を出る頃、
少しだけ背筋が伸びた気がした。
継承という言葉が、
なぜか“ずっと続いていく優しさ”に思えたからだ。
まとめ──静かに灯る“ひとすじの希望”

心のどこかに小さく灯る光がある。
それは大げさな救いや逆転劇ではなく、
「弱さを抱えたままでも、生きていける」
という、とても静かな明かりだ。栄治も耕造も加奈子も、
誰も完璧じゃなかった。
すれ違い、怒り、沈黙、後悔──
そのどれもが、彼らを“弱さごと”形作っていった。
人は、欠けたまま進んでいい。
そしてその欠けた部分が、
いつか誰かの支えになることもある。
作品の中で繰り返されるのは、
“勝つこと”より
“立ち上がり続けること”の尊さだ。
そして20年という長い季節の中で、
夢はようやく形を変えて、そっと戻ってくる。
私たちの人生もきっと同じだ。
思いどおりにならない日が続いても、
足が止まってしまう夜があっても、
それでもどこかで、
遅れて届く希望が待っている。
この作品の余韻は、喧騒とは無縁の“深い静けさ”だ。
本を閉じたあと、胸の奥に
ゆっくり沈んでいくような優しさがある。
だからこそ私は、
この物語を“大人の読書時間”として大切にしたい。
そしてあなたにも、
弱さを抱えたまま灯る光を
そっと手に取ってほしいと思う。
FAQ(よくある質問)
Q1. 『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬を知らなくても楽しめますか?
はい。むしろ競馬の知識がない読者のほうが、人物の心情に素直に入り込める作品です。
競馬は「舞台装置」であり、物語の中心は“弱さと継承”という人間ドラマです。
Q2. 小説とドラマ版ではどこが違うのでしょうか?
大きな違いは時間軸(1997–2017 → 2011–2030)と、
人物のドラマ的再構築です。
ドラマはより“家族ドラマ色”が強く、
原作はより“内面の静けさ”が深く描かれています。
Q3. 物語のテーマは何ですか?
一言でいえば、「弱さを抱えたまま生きる人たちの物語」です。
勝つことよりも、負け続ける時間をどう歩くか──
その姿に、読む者は静かに心を重ねていきます。
Q4. どんな読者におすすめですか?
・夢に踏みとどまっている人
・家族との距離に悩んでいる人
・人生に“遅れて届く答え”を探している人
こういう人ほど、物語の余白に救われるはずです。
Q5. 辛いシーンはありますか?
あります。ただしそれは残酷さではなく、
“生きていく上で避けられない痛み”として描かれます。
読み終えたあとには、その痛みの奥にある
静かな優しさがじんわりと残ります。
Q6. 競走馬ロイヤルホープのモデルはいますか?
あくまでフィクションですが、
日高の牧場が抱える現実や、庭先取引の文化を背景に
“実在しそうなリアリティ”で描かれています。
モデル探しよりも、馬が“人の影を映す存在”として機能する点が魅力です。
Q7. 読書初心者でも読み切れますか?
500ページ超と長めですが、
文章は驚くほど滑らかで読みやすいため問題ありません。
章ごとに“季節が変わるような静かな展開”が続くので、
気づけば物語に寄り添っているはずです。
参考・出典
- 『ザ・ロイヤルファミリー』早見和真(新潮社)
- 新潮社公式サイト:
 新潮社新潮社の公式サイト。書籍、文庫、新書、雑誌、コミック、デジタルコンテンツの最新情報。書籍検索、文学賞の紹介、採用情報
新潮社新潮社の公式サイト。書籍、文庫、新書、雑誌、コミック、デジタルコンテンツの最新情報。書籍検索、文学賞の紹介、採用情報 - TBSドラマ公式サイト「ザ・ロイヤルファミリー」:
 TBSテレビ|ときめくときを。TBSテレビが放送する番組情報満載の公式サイトです。TBSが放送するテレビ番組の予告やあらすじなど、テレビ番組情報はこちらから!
TBSテレビ|ときめくときを。TBSテレビが放送する番組情報満載の公式サイトです。TBSが放送するテレビ番組の予告やあらすじなど、テレビ番組情報はこちらから! - JRA(日本中央競馬会)公式データベース:
 JRA日本中央競馬会JRA日本中央競馬会の公式ホームページです。出馬表、オッズ、払戻金、レース結果などの確認やインターネット投票が行え、また、全国の競馬場、ウインズのイベント情報など中央競馬に関することを掲載しています。
JRA日本中央競馬会JRA日本中央競馬会の公式ホームページです。出馬表、オッズ、払戻金、レース結果などの確認やインターネット投票が行え、また、全国の競馬場、ウインズのイベント情報など中央競馬に関することを掲載しています。 - 公開インタビュー・ニュース記事(キャスト・制作コメント・放送関連情報)
- 公開情報:テレビ番組表、プレスリリース、公式SNS
本レビュー記事は、公式情報・一般公開の報道・出版社情報をもとに執筆し、
作品内容の核心に触れすぎない範囲で構成しています。




コメント